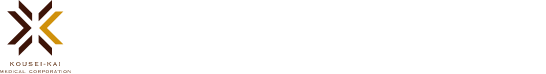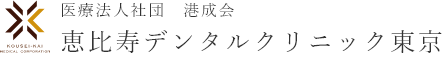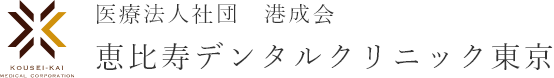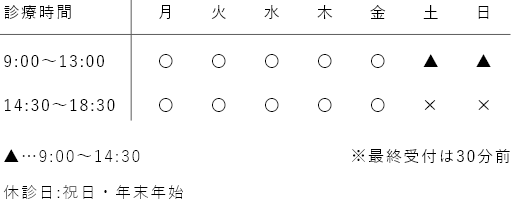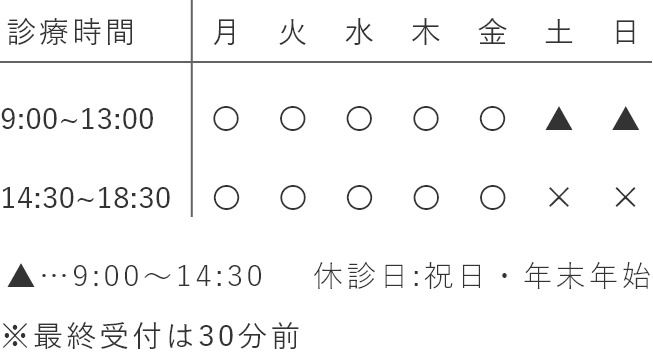こんにちは、恵比寿デンタルクリニック東京の歯科衛生士です。今回は、普段の生活習慣で歯周病予防のためにできることをご紹介いたします。
歯周病の主な原因は、細菌感染です。
歯ぐきが歯周病菌に感染することで、さまざまな症状を引き起こします。歯周病は生活習慣病の一つであり、生活習慣を改善することで、効率よく予防することができます。
歯周病予防におすすめの食べ物
歯周病予防には、以下の栄養素や成分を含む食品がおすすめです。
歯ぐきを健康に保つ「ビタミンC」
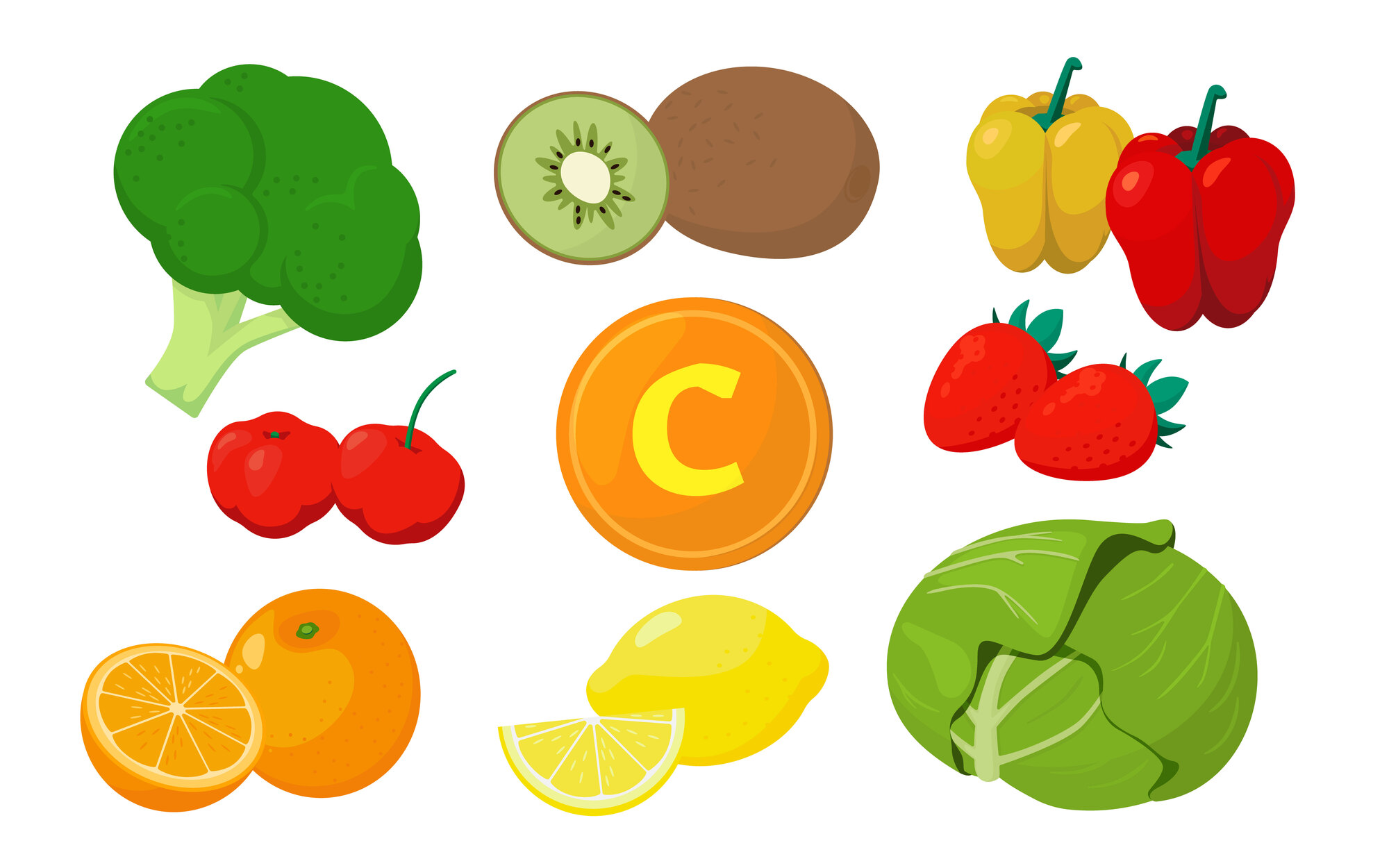
歯ぐきを構成するコラーゲン繊維を作る上で、ビタミンCは欠かすことのできない栄養素です。歯ぐきの状態が良ければ、歯周病のような感染症にかかりにくくなります。そんなビタミンCは、アセロラ、キウイフルーツ、ブロッコリー、レモンなどに豊富に含まれています。
歯周病菌の活動を抑える「乳酸菌」

乳酸菌というと、腸で働く善玉菌として有名だと思います。腸内で悪さをする悪玉菌の働きを抑制する作用が期待できます。
実は、お口の中でも同じようなことが言えます。歯周病菌は、お口の中における悪玉菌であり、乳酸菌LS-1や乳酸菌L8020など、一部の乳酸菌がその活動を抑えることがわかっています。これらは市販のヨーグルトやタブレットに配合されています。
歯の再石灰化に寄与する「カルシウム」
カルシウムは、歯を構成する主な成分です。カルシウムをしっかり摂取することで、脱灰した歯の再石灰化が起こりやすくなり、歯の表面に汚れがつきにくくなります。
その結果、細菌の繁殖が抑えられ、歯周病予防に寄与します。カルシウムを豊富に含む食べ物としては、乳製品や大豆製品が挙げられます。
避けたほうが良い食べ物
一方で、歯周病予防のために避けたほうが良い食品もいくつかあります。
細菌の繁殖を促す食べ物

歯周病菌は、お口の中に残った食べカスなどをエサとして繁殖します。そのため、チョコレートやアメ、キャラメルのようなネバネバした食べ物はできるだけ避けるのが望ましいです。
また、一見問題ないように思える清涼飲料水も、たくさんの糖質が含まれ、お口の中に残存しやすくなっているため要注意です。
歯ぐきの炎症を促す食べ物
歯周病の主な症状は、歯ぐきや歯を支える骨の炎症反応です。細菌感染によって、歯周組織に炎症が起こり、腫れや痛み、出血などをもたらします。ですから、炎症反応を促進するような暑い食べ物や辛い食べ物はできるだけ避けるようにしましょう。
栄養バランスの悪い食べ物
歯周病は、細菌感染症の一種なので、予防するには全身の免疫状態にも配慮する必要があります。
例えば、インスタントラーメンや冷凍食品、コンビニエンスストアのお弁当など、栄養バランスが悪い食べ物ばかり食べていると、全身の免疫力が下がって、歯周病菌に感染しやすくなります。できれば自炊をして、新鮮な野菜、フルーツ、肉、魚などをバランスよく摂取するように努めましょう。
食べ物以外に気をつけること
歯周病は生活習慣病の一種であり、予防のためには食生活以外にも気をつけたい点があります。
よく噛んで唾液をたくさん出す
唾液には、抗菌作用・殺菌作用・自浄作用などがあります。食事の際は、よく噛んで唾液腺を刺激し、たくさんの唾液を分泌することで、歯周病菌の繁殖や働きを抑えることができます。
適度な運動と十分な睡眠で免疫力を高める
免疫力は、食事だけでなく、運動や睡眠によっても高めることができます。裏を返せば、運動や睡眠が不足した生活を送っていると、免疫力が低下して歯周病などの感染症にかかりやすくなるため、注意が必要です。
禁煙する
タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素は、歯ぐきの血流を悪くし、酸素や栄養素の供給を妨げます。その結果、細菌に感染しやすくなり、歯周病のリスクが上昇します。喫煙習慣は歯周病を重症化させる主な原因です。
ストレスを解消する
ストレスも歯周病のリスク因子として有名です。仕事や勉強のストレスを、運動や遊びによって上手に解消することが重要です。週末などには趣味の時間を作って、ストレスを緩和しましょう。
歯周病は日々の予防や検診が大切です
食事や生活習慣に気を配ることで、歯周病を効率よく予防できます。このブログを参考に、生活習慣を見直してみてください。
また、歯科医院でメンテナンス・歯科検診を定期的に受けることで、歯周病の予防効果をさらに高めることができます。
歯周病が気になる方、その他少しでも歯について気になる方は、恵比寿デンタルクリニック東京までお気軽にご相談ください。
こちらもご覧ください。